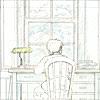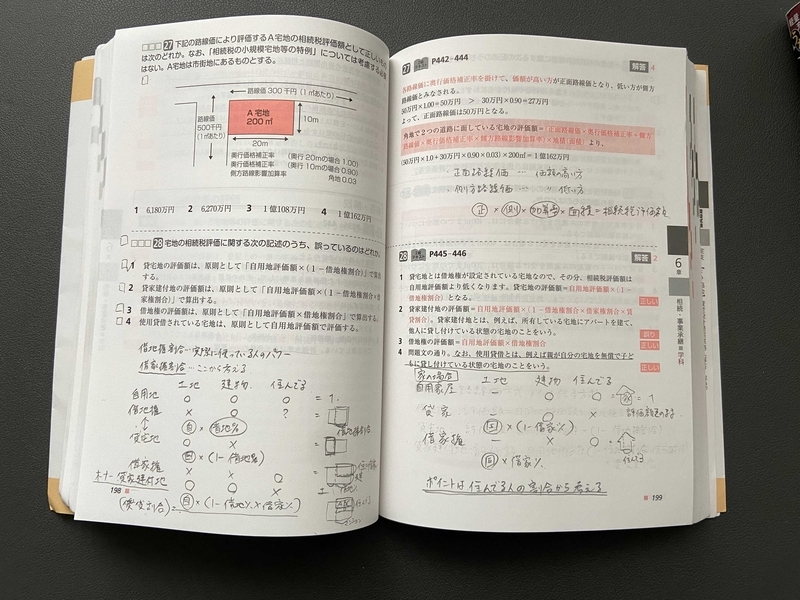京都で久々にラーメンを食べた。
その日は午後から用事があり、お昼前にランチを探した。寒い冬の京都ということで、無性にラーメンが食べたくなった。たまたま昔好んで行った塩ラーメンの店が近くにあることを思い出した。しかし、その店の開店にはまだ少し時間がある。待っていれば次の予定に間に合わない。仕方なく、Googleマップを開いて近くの店を探すことにする。
舌はもうラーメンを欲していたので、「ラーメン」と打ち込んで検索すると、レビュー件数の爆発的な店がみつかった。どうやらミシュラン常連のラーメン屋らしい。しかもほんの10mほど目と鼻の先の距離にある。店先をのぞくと並んでいる人も少なく、人気店のわりにすぐ入れそうだ。ランチに迷う時間もなかったので、この店に入ることにした。
店内はとにかく活気があった。カウンターには西洋人の旅行客らしき夫婦がいて、テーブルには中国人のファミリーがいた。私のように1人で気軽にラーメンを楽しみに来ている日本人客も何人かいた。まずメニューを手に取ると、左に日本語、右に英語ときれいに2分割されて2カ国語対応している。ラーメンはすべて1400円以上で中には2000円を超えるものもある。決済はすべてキャッシュレスで現金勘定はない。そこでやっと「観光客向けの店に入ったのだな」と認識した。
私はその店の一番スタンダードなラーメンを注文した。鰹節がしっかり効いたスープで美味しい。麺は細麺で一乗寺にあるような昔ながらの京都ラーメンを思わせる。あとでゆずの皮やとろろ昆布で味変する用意もある。スープには日本らしさがあり、麺には京都らしさがあり、盛りつけにはミシュランらしさがあった。おもてなしには完璧なラーメンだった。勘定しようとすると、店長らしき人が「朝早くから来ていただいてありがとうございます」とさりげなく声をかけてくれた。接客も料理の味も、とても気持ちの良いものだった。
しかし同時に、店を出たあとに複雑な気持ちになった。私の中の何かが不満だった。ただこの時はその正体をうまく言語化できずにいた。

京都によく行くようになったのは、バンド活動が再開されたからでもある。ドラムは大学時代から一緒にバンドをやっていたK先輩だ。Kさんは京都のとあるジャズバーで働いている。40年超の歴史があり、マスターは70代の老舗店だ。卒業してから1年ほどで脱サラして、あとはずっとこのジャズバーで働いている。
それほど給料のいい仕事ではないらしく、コロナ前までは常に金欠のようだった。飲みに行っても一緒にいたメンバーで多めに払うことが多かった。けれども、最近はなんだか羽振りがいい。スタジオ代はきっちり払ってくれるし、練習後に飲みに行くとシフトがあるからと先に出るのだが、少し多めに置いて行ってくれる。
「Kさん、何かあったんですか?」と聞くと、
「給料2倍になってん!」と返ってきた。
「店に外人ばかり来るようになって、めっちゃ儲かってんねん!」とのことだった。
表情もコロナ前よりもちょっぴり明るくなった気がする。
音楽を主体とした店は、経営的に行き詰まりやすい。趣向がコアになると客層が固定化するからだ。学生時代に行った店は、この10年ほどでいくつ閉店したことだろう。競争の熾烈な京都の繁華街で生き残るには、常連客だけでなく観光客向けにサービスすることも必要になる。インバウンドの影響はこんなところにも出てきているのだ。
むろん京都の観光地化は今に始まったことではない。以前からバス停で待っていると旅行客からしばしば道を聞かれたし、海外情勢によって旅行客の人種は変わるものの、観光の街であることは変わっていない。けれども以前に私が住んでいたときや、コロナ前にアジア人が爆買いしにきていたときとは、また違った現象が起きているように思う。
それは私たちのパーソナルな生活空間にまで、旅行客が来るようになったということだ。彼らは清水寺や嵐山を求めるのではない。唯一無二の体験を求めて日本に来る。以前の京都は、観光地とそれ以外はきれいに分かれている印象だった。しかし一般的なガイドブックに掲載されている場所を訪れる体験への価値は低くなり、希少な体験を求めて旅行客が訪れる。K先輩の働くバーは、その格好のスポットになっていた。
こんなことを考えるようになったのは、東浩紀『観光客の哲学』を読んだことが影響している。本書では「観光客」とは、自由気ままにその国を訪れて、偶然その国の文化に触れて帰っていくような存在のことをいう。東の主張は、「観光客」のような流動体な存在が、分断された社会を解きほぐすためのヒントになるのではないかということだ。
本書の中にこんな文章があった。
現代は決してナショナリズムの時代ではない。かといって、単純にグローバリズムの時代でもない。現代ではナショナリズムとグローバリズムという2つの秩序原理は、むしろ政治と経済の2つの領域にそれぞれ割り当てられ重なり共存している。僕はそれを二層構造の時代と名づけたいと思う。 (『第3章 二層構造』 より引用)
冒頭のラーメン屋を出たあと、感じた違和感の正体についてしばらく考えていた。本書を読みながら思った。
私は生まれ育ったこの街で、いつからか観光客になったのかもしれない。
Kさんのジャズバーは、以前はそれほど居心地のいい場所とは思えなかった。狭苦しい空間に常連客が多くて馴染めなかった。それでも文化的スポットとして注目されていると聞くと、また行ってみたくなった。
私はここでもまた観光客になろうとしている。
京都はグローバルに開かれた文化都市であるから、街が変わっていくのは当然の成り行きであるし、年月が経っても微々たる変化しかない田舎と比べると、それは歓迎すべきことなのだろう。
私はミシュランのラーメン屋に対して不満だったのではない。観光客にはなりたくなかったのだ。自分の中にある二層構造を受容できていなかった。観光地はグローバリズムと無縁ではいられない。あの頃の京都を残しておいてほしい、存続しておいてほしいと願うのは、単に一時代を経験した人による個人的な願望にすぎない。そんなものを大事にしていると、街の方が廃れてしまう。京都という街は、私にとってグローバリズムとローカリズムの二層構造を意識する特別な場所に変わりつつある。
次に京都でひとりランチをする機会があれば、今度は昔行った塩ラーメンの店に行ってみたい。夜を過ごす日があれば、Kさんのジャズバーにも行きたい。私はひとつの街を両方の側面から訪ねてみることができる。そんな場所はここ以外にはない。
<参考>
東浩紀『観光客の哲学』(ゲンロン叢書, 2017)